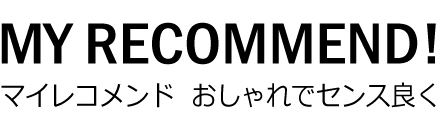長寿のお祝い【還暦・古稀・喜寿・米寿】祝い方や相場を解説
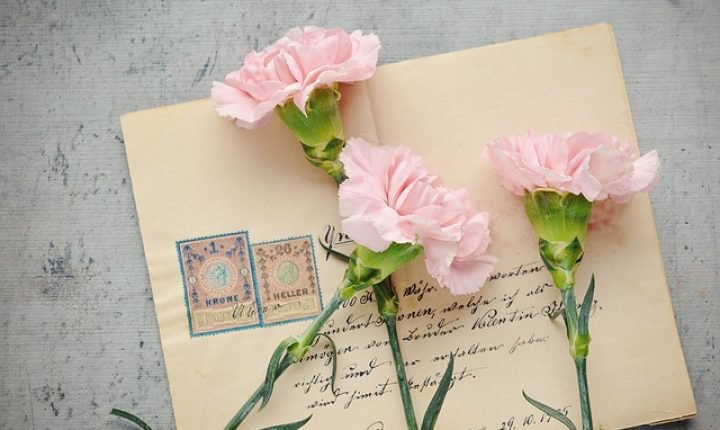
長寿祝いとは、生まれた年を1歳とする「数え年」で、61歳になる年を「還暦(かんれき)」、70歳は「古稀(こき)」、77歳は「喜寿(きじゅ)」、80歳は「傘寿(さんじゅ)」というように、長寿祝いには様々な種類があります。
こちらでは、長寿祝いとして還暦や古稀、喜寿や米寿などお祝いの仕方や相場、贈り物などについて解説します。
記事中で紹介している画像一覧長寿祝いとは?
-

そもそも「長寿祝い」とは、生まれた年を1歳とする「数え年」で、61歳になる年を「還暦(かんれき)」、70歳は「古稀(こき)」、77歳は「喜寿(きじゅ)」、80歳は「傘寿(さんじゅ)」…というように、元気に長生きされる方々へのお祝いと、これからも元気でいて欲しいという思いを込めて祝福するものです。
長寿祝いの種類や年齢について
「長寿祝い」は「賀寿(がじゅ)のお祝いとも呼ばれますが、日本での始まりは奈良時代とされ、当時は初老の40歳からお祝いをしていたとされています。
長生きをするのが難しかった時代とは違い、現在の40歳に初老という言葉は何だか変な感覚ですが、それだけ現代は長生きで若々しくいられるということでもあります。
ちなみに賀寿は108歳が「茶寿(ちゃじゅ)」、111歳が「皇寿(こうじゅ)」、120歳が「大還暦(だいかんれき)」となります。
長寿(還暦)祝いの祝い方や贈り物について
-

「還暦」は数えで61歳(満60歳)の年にお祝いをすることが一般的です。
還暦とは60年周期で一巡する干支にちなんだ呼び方で、生まれた干支に戻ることから赤ちゃんに還るとされており、魔除けとされる赤色のものを贈ってお祝いします。
赤い頭巾やちゃんちゃんこを贈る風習は、このような意味合いからきているものです。
退職の年齢が65歳まで引き上げられ、また退職後に新たな仕事を始められる方もたくさんいる現代。
60歳を迎えた方に「長寿祝い」として還暦をお祝いするのは少し違和感を感じるという方もいらっしゃいますが、やはりいつまでも健康で快活でいて欲しいと願いを込めて家族でお祝いをされることも多いですよね。
現代では60歳と言っても若々しい人が多いですから、還暦祝いとして派手にお祝いされることには抵抗を感じる方も多くいらっしゃいます。
最近では、これからも元気でいてもらえるようにと趣味の品や旅行などの贈り物が好まれる傾向にあります。
緑寿(ろくじゅ)のお祝いの贈り物について
また近年では、定年を迎える66歳の「緑寿(ろくじゅ)」の賀寿にお祝いをするケースもみられます。
緑寿は百貨店から提唱された新しい賀寿で、元気で活力ある緑色をテーマにお祝い品を贈るようになっています。
こちらは定年退職の御祝と合わせて贈るのも喜ばれ、一緒に外食や旅行に行かれるのも素敵な贈り物となるでしょう。
他にも、70歳の「古稀」は77歳の「喜寿」と合わせて高貴な紫色がお祝いに相応しい色とされていますので、その色にちなんだ品物を贈ると良いでしょう。
また、80歳の「傘寿」、88歳の「米寿(べいじゅ)」は金茶色または黄色のお祝い色、90歳の「卒寿(そつじゅ)」、99歳の「白寿(はくじゅ)」は白がお祝いの色となっています。
長寿祝いの祝宴やお祝いの席の設け方
-

長寿祝いとして、祝宴の席を設けられる場合などは、ご家族やお孫さん、ご親戚の方々など身内で集まってお食事をされたり、ホテルや温泉で一泊したりと祝い方は様々です。あくまでご本人の意向や体調に合わせて企画するように心がけましょう。
関連記事はこちら
長寿祝いの相場やのし、表書きについて
-

還暦祝いを含め、「長寿祝い」の金額には特に決まりはありませんが、1万円から10万円くらいが目安となります。
お子様からご両親へ贈る場合などは、一般的には2万円から3万円程度が最も多い相場になります。ご親類などの場合は、お相手との関係によって決めると良いでしょう。
表書きは、還暦であれば「祝還暦」、古稀であれば「祝古稀」などとなります。そのほか、「寿」、「寿福」なども可です。
熨斗付き紅白(または金銀)蝶々結びの水引きをつけてお祝いを贈ります。
長寿祝いのお返しは必要?
長寿祝いのお返しは基本的には不要ですが、いただいた額の半額から三分の一程度の品物をお返しすることも。
内祝いや紅白饅頭や赤飯、賀寿の漢字を入れた風呂敷や陶器を記念品として贈って喜びを分かち合うのも良いですね。
「長寿祝い」を通じて、これまでの長生きを共に喜び、これからの健康を共に願い、これからも共に過ごしていく絆を深める機会になると素敵です。