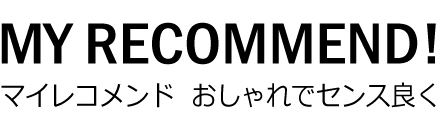2025年のお月見はいつ?十五夜や中秋の名月、お供え物も解説

満月の夜に、月見団子とススキを飾った縁側で月を眺めながらお酒を一杯、なんてイメージが浮かぶ方もいらっしゃるのではありませんか?
日本には「四季」を通じて自然の美しさを楽しむ文化がありますが、秋の風物詩のひとつが「お月見」ですよね。
目次
2025年の「中秋の名月」は10月6日月曜日
-

2025年の「十五夜(じゅうごや)」、「中秋の名月(ちゅうしゅうのめいげつ)」は10月6日(月曜日)、「十三夜(じゅうさんや)」は11月2日(日曜日)です。
平安時代頃に日本に伝わったとされている「お月見の習慣」。実は月と日本人の歴史は古く、縄文時代には月を神聖なものとし、愛でる習慣もあったようです。
日本人にとって深い繋がりのある風習「お月見」とは一体どういったものなのでしょうか?
こちらの記事では、お月見の起源のほか、2025年の十五夜(中秋の名月)や十三夜、芋名月、栗名月、豆名月、「お供えのもの」などについても解説いたします。
お月見の時期はいつ?お月見の起源について
-

旧暦8月15日の月は「十五夜」や「中秋の名月」、旧暦の9月13日の月は「十三夜」と呼ばれ、この時期は一年のなかで最も美しい月を鑑賞できるとされてきました。
古来中国では、十五夜に円満を願って丸い月餅を食べ宴を開く中秋節の風習があり、それが平安時代に貴族の間に広まって十五夜の宴になったとされています。
十五夜(中秋の名月)、十三夜(じゅうさんや)について
-

日本のお月見の習慣は、日本の月信仰の風習と、古来中国の風習が合わさり今のような形になったとされています。
そして、9月中旬から下旬(旧暦8月15日)の月は「十五夜」(中秋の名月)と呼ばれ、その約一ヵ月後の10月中旬から下旬(旧暦9月13日)の月を「十三夜」と呼び、日本独自に発展したものともいわれています。
江戸時代には、庶民の間にもお月見の風習が広がり、宴を開くだけでなく秋の収穫を感謝する儀礼の意味合いが加わり、現在のような月見が行われるようになったとも伝えられています。
芋名月、栗名月、豆名月とは?
十五夜は、里芋の収穫時期と重なるため別名「芋名月」とも呼ばれ、十三夜は特に栗や豆の収穫時期と重なることから「栗名月」や「豆名月」とも呼ばれています。
なお、片方の月見だけをすることを「方見月(かたみづき)」といって縁起が悪いとも言われています。
お月見のお供え物について
-

今日のようなお月見の形は、江戸時代頃にできたもので、お月見のお供え物に「月見団子」や「秋の七草」のなかで魔除けの効力もあるとされる「ススキ」を飾ったり、「さと芋」や「栗」、「柿」などその時期に収穫された農作物やお神酒などをお供えするようになりました。
お供え物の飾り方
お月見の供え物としては、丸い月見団子が広く知られていますね。
お米から作られた上新粉や白玉粉で月に見立てた団子を作り、十五夜の15個、十三夜の13個、または一年の月の数と同じ12個を飾りますが、地域によっても違いがあります。
また、お月見の時期が「秋のお彼岸」とも重なることから、おはぎを供えたり、地域によっては団子の代わりに里芋や、十三夜には栗や豆といったその時期に収穫された月のように形も丸いものを供えるところもあります。
月見団子の違い

お供え物の月見団子も地域によって少し異なります。
一般的に月見団子としてイメージされる丸い形の団子をはじめ、餡が団子の中に入ったタイプや、団子が餡で包まれたもの、関西地方で見られる里芋に似せた楕円形の団子にこし餡がまかれたものなど、地域によって形も異なります。
関連記事はこちら
秋の実りの収穫を感謝する気持ち
-

古代から日本人は、四季の移ろいの中で自然の力を借りながら暮らしてきました。
そして、秋の実りの収穫を感謝する気持ちが、月見の習慣と重なっていったというのが日本らしいですね。
日々、目の前の忙しさに追われる現代ですが、ふと立ち止まって夜空を見上げ、綺麗な月を鑑賞する、そんな時間を持ってみるのも良いですね。